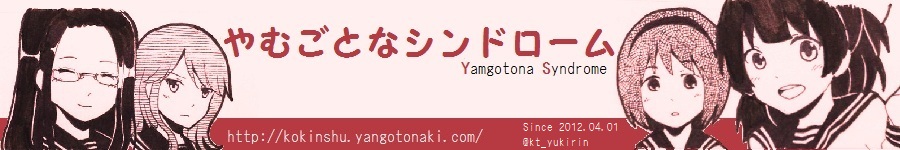古文の書き方 助動詞⑤ 推量
今回より、助動詞界のメインジャンル、推量を紹介し奉らむ。混乱は最も多きところなれど、概念的には時制より遥かにやすし。べし
接続は、終止形なり。手前の動詞がラ行変格活用の場合、連体形接続なり。……要は、手前はシンプルなるウ段にすべし、といふことなり。(×するべし ○すべし、×ありべし ○あるべし)活用形を示し奉らむ。
| 助動詞 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| べし | べから | べかり | べかる | (べかれ) | ク活用型 | ||
| べく | べし | べき | べけれ |
形容詞系なれば、上の列はカリ活用なり。助動詞の手前にべしをつかふ折のみ採用すべし。 さて、推量の助動詞は、意味ぞ難し。全6種あり。
④当然(基本義)
当然の帰結、根拠の強き推量をあらはす語なり。英語にいふshould、現代語にいふ「当然-はず」。ほかの意味は、すべてこの当然の意より派生するものなり。このニュアンスを得ば、ほかの意味は心得ずとも、古文を「書く」ことには、つやつやさはりなからむ。
この状況ならば、必ずかくあり。といふ意味なり。
①推量
主語が3人称なる折に、動作をすること、状態にあることを推量する語なり。上に「つ」「ぬ」があらば、「つ」「ぬ」は推量を強める強意の助動詞となるなり。

推量にて重要なることは、「根拠なし」といふことなり。上の絵にてたとふれば、汗をかきぬることは事実なれど、長距離走れり、といふ根拠としては薄し。体質的な問題、汗にはあらで水浴び後、といふ可能性もあり。かくのごとく、根拠なき折には、推量の助動詞を採用すべし。
(※根拠ある折には推定の助動詞を採用すべし。そは別なる機会にせむ。)
②意志
主語が1人称なる折に、動作をすること、状態にすることを決意する語なり。己の次の行動への推量、といふことも可なり。…こは、心得がたければ無視せなむ…。
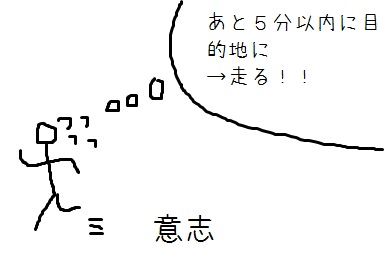
かくのごとく、己に対する命令と心得てもよからむ。上記の例のごとく、
⑥適当
主語が2人称なる折に、動作をすること、状態にすることを勧むる語なり。命令の弱体化版と心得てもよからむ。
⑤命令(・必要・義務)
現代語に最も近き意味なり。直観にて書きても、さしもさはりなからむ。適当の強化版と心得てもよからむ。
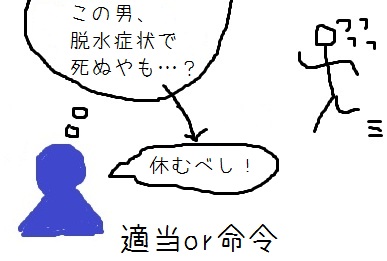
③可能
貴殿は知るや、もとより、漢文にては「可」で「べし」と読むことを。…常識にや?と、いふことにて、
意味のいと多きに、心づきなく覚えたまふ御方も多からめど、実は、「べし」を記憶すればさらに4つの助動詞は理詰めにてぞ意味の特定が可能なる。後が楽なれば、①推量②意志③可能④当然⑤命令⑥適当の番号順に頭文字をとりて、「すいかとめて」と記憶すべし。
「す……す…す…推量………い…い……意志…」と、はじめのうちはかくのごとき様なれど、やがてならひたまふべし。
む・むず ー弱体化べしー
接続は未然形なり。「むず」は、「むとす」の変形版なれば、活用形よりほかに、「む」とたがふところなし。活用形を示し奉らむ。
| 助動詞 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| む | ○ | ○ | む | む | め | ○ | |
| むず | ○ | ○ | むず | むずる | むずれ | ○ | サ行変格風 |
やすからむ。未然形、連用形、命令形はとらず。文末か、助詞の直前に来ること多し。
意味を紹介し奉らむ。
①推量
②意志
③勧誘・適当
勧誘は、命令の弱体化と心得るべし。さすれば、こも「べし」との重複なり。
--------ここまで「べし」と重複---------
④仮定・婉曲
連体形の折に発動する意なり。我は使用すること多し!区別とて、
- 名詞の前→婉曲(~ような)
- 「は」「こそ」等の助詞の前→仮定(~としたら)
(ex)
①「死なばや」といはむ女君が死ぬるためしなし。
②死ぬべく覚えども、出家せむはさすがにつらからむ。
(①「死なばや」といふような女性が死ぬるためしなし②死ぬべくおぼえど、出家するとせば、さすがにつらからむ)
といふイメージなり。心得たまふや?
む vs べし
「む」と「べし」の相違点は、その意味の強さにあり。「む」<<<<<<「べし」
といふ大小関係を記憶せなむ。
今回は以上なり。次回は打ち消しの助動詞を3種類紹介し奉らむ。
< 前回の記事 古文の書き方 助動詞④ 実践編 | 次回の記事 古文の書き方 助動詞⑥ >