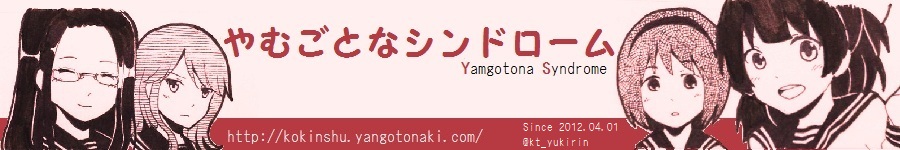古文の書き方 助動詞③ 存続
今回は、存続の助動詞「り」「たり」を紹介し奉らむ。今まで学びし助動詞に比ぶれば、さしも難からず。接続に注意すべし。今回は趣向を変へ、「り」と「たり」の相違点より説明し奉らむ。り vs たり
「き」vs「けり」、「つ」vs「ぬ」と異なりて、「り」vs「たり」には、意味的な相違点はなくて侍り。この二つは、使用する動詞による違いあり。現代語における「れる」「られる」のごとし。手前の動詞が
- 四段活用、サ行変格活用の場合→「り」
- それ以外の場合→「たり」
といふことのみなり。シンプルならむ!
ここにて、接続も紹介し奉らむ。接続は、
- 四段活用の場合→已然形+「り」
- サ行変格活用の場合→未然形+「り」
- それ以外の場合→連用形+「たり」
(ex)書けり。 学べり。 せり。 あり。(→★を参照すべし) 死にたり。/死せり。
「り」の接続は、不良の当て字のごとく、「サ未四已」→「さみしい」といふ記憶法あり。よろしと思ひたまはば。
★「ありたり」??
「あれり」とせむが、言葉の雰囲気的にはよからむ、と思ひ侍り。しかれども、「あり」は、ラ行変格活用なれば、原則、「たり」を使用すべきものなり。
古語辞典に曰はく、り、たりの語源は「あり」、「てあり」ならし。しからば、「ありたり」は、もとより「ありてあり」なれば、「あり」の重複あるべし。しからば、「あり」は、すでに「り」「たり」の意味を含む語として思ひなさむ。
り・たりの活用・意味
活用形を示し奉らむ。| 助動詞 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| り | ら | り | り | る | れ | れ | ラ変型 |
| たり | たら | たり | たり | たる | たれ | たれ | ラ変型 |
つづいて、意味を紹介し奉らむ。
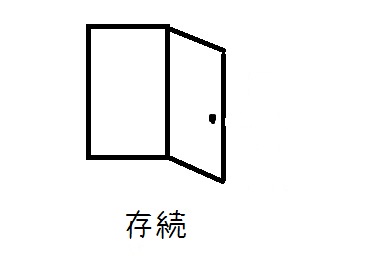
①存続
ある動作が完了し、その動作の結果が続きたることを表現する語なり。こが基本の意味にて侍り。
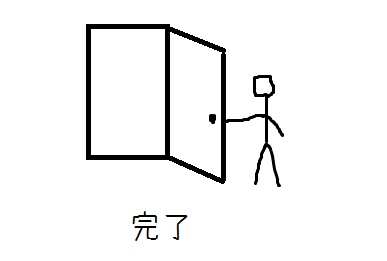
②完了
こは、単にある動作が完了することを表す語なり。古語辞典を見るに、「つ」「ぬ」のごとき相違点はなかめり。解釈上、「…!?こは、存続に……あらざらむ……。如何にせまし……。」といふ折用に作られしものならむ、と思ひ侍り。完了の助動詞として使はむは、いとめでたきことにあらざらむ、と思ひ侍り。「つ」「ぬ」を使用せむ。
今回は短けれど、以上なり。次回は実践編とて、今まで学びし「き」「けり」「つ」「ぬ」「たり」「り」を用ゐて、例文を古語に翻訳せむ。
< 前回の記事 古文の書き方 助動詞② | 次回の記事 古文の書き方 助動詞④ 実践編 >